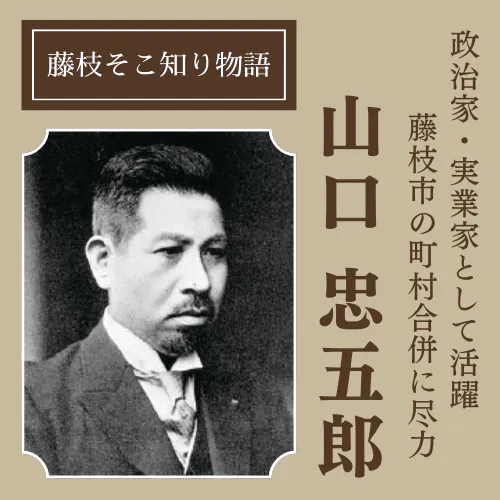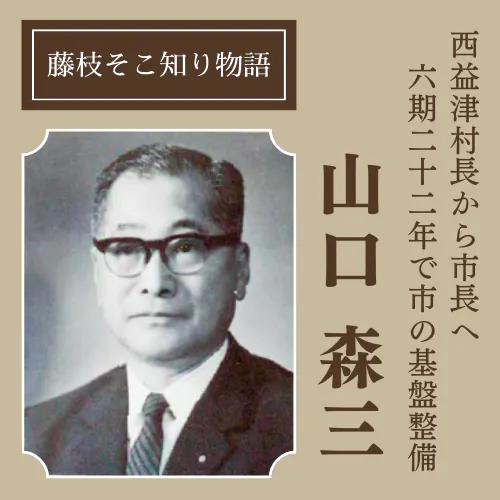藤枝市は、令和6年1月1日に、昭和29年の市制施行から70年、そして大正13年を起源とするサッカーのまちとしての歩みも100年となる記念すべき年を迎えました。
これまでに数多くの偉人たちが藤枝に関わってきました。
このコーナーでは、藤枝に纏わる様々な偉人たちをご紹介していきます。
島田・藤枝・焼津に八十一箇所・八兵衛さん
疫病除け・洪水除けが主 地域地域で信仰継承
志太地域にのみ存在する地域の特殊な信仰に「八兵衛さん信仰」があります。伝承によると、元禄時代にこの地域で疫病が発生し、通りかかった旅の僧が持っていた薬によって疫病を治めたということになっています。また、亡くなる時に「我を祀らば悪病に罹ることなし」と遺言したとも伝わっています。その僧が「八兵衛さん」として今日まで各地域で信仰され続けているわけです。
その多くが瀬戸川、栃山川、木屋川、黒石川の付近に祀られているのも特徴で、島田・藤枝・焼津に八十一箇所確認されています。
焼津の石津や田尻、石脇下では「薬売りの八兵衛さん」と称され、また、旧大井川町では、小長谷家に婿入りして、小長谷八兵衛となったとしています。特徴的なのは、町内会単位の規模でずっと信仰され続けているということです。
八兵衛さんの正体
八兵衛さんの正体は、実に様々に伝えられていて、その主な説をご紹介します。
◎六部僧説 諸国巡礼をし、全国六十六カ所の有名な寺に法華経写経を奉納して歩く行脚僧だった。
②修験者説 修験者で、当地に来た折り疫病が蔓延していたので加持・祈祷により疫病を治した。六部僧説も含め「弘法大師の再来」と称された。
③小長谷八兵衛説 紀伊国(和歌山県日高郡川中島)の出身の吉田八兵衛で、若い頃から漢方医学を説いて遍路姿になり諸国を遍路して多くの病人を救った。旧大井川町の小長谷家の婿養子となり周辺の病人を漢方医学により治した。
④中嶋八兵衛説 三重県尾鷲の回船問屋、土井八郎兵衛の娘と結婚した中嶋八兵衛という説。たまたま陸路になった折、持っていた薬で地域の人々を助けた。
⑤人柱・川除け説 大井川の洪水が直撃し被害も甚大で堤防普請の際に八兵衛が人柱となった。堤防上に祀られているのは川除けのご利益のため。
◎行き倒れ説 最期は行き倒れとなったので、行き倒れの旅人は祟り神となるため、それを祀ればご利益があるとして祀られた。
様々な八兵衛の表記
先の伝承が様々なように、それぞれの墓や供養塔に書かれた銘も実に多岐です。「紀伊国川中嶋小長谷八兵衛」が最も多く、そのほかに「西国川中嶋小長谷八兵衛」「紀ノ国川中島ヲハセノ八兵工様」「八郎兵衛」「川中島をはせ」「小長八兵衛」「八兵衛之塔」「八兵衛之墓」などとなっています。
八兵衛さんの供養
現在も多くの地域で八月十五日前後に供養が行なわれています。僧侶の読経が終わるとお年寄りが「オショーヤ」と言うご詠歌を唱えたり、墨書した「紀伊国川中嶋八郎兵衛」の札が厄除けの札として地区の家庭に配られたりします。また「山は八つ、谷は九つ、身は一つ、我行く末は柊の里」の言葉を三回唱えると病気にかからないという言い伝えもあります。