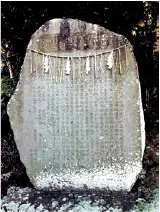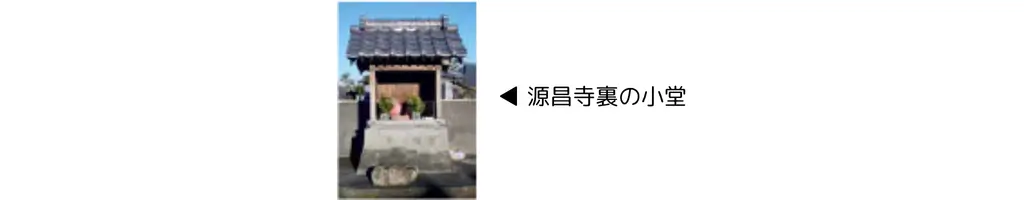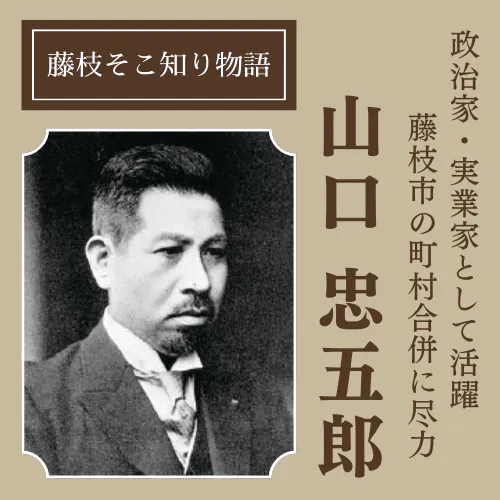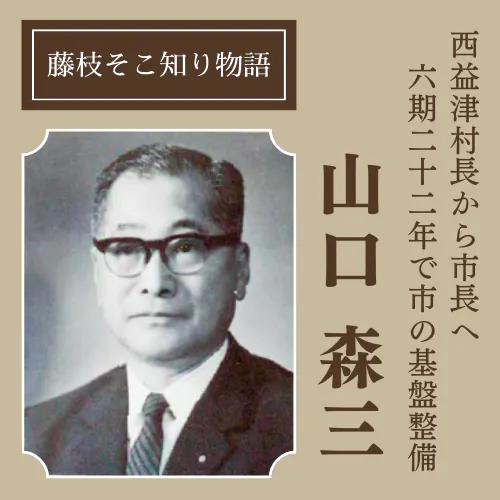藤枝市は、令和6年1月1日に、昭和29年の市制施行から70年、そして大正13年を起源とするサッカーのまちとしての歩みも100年となる記念すべき年を迎えました。
これまでに数多くの偉人たちが藤枝に関わってきました。
このコーナーでは、藤枝に纏わる様々な偉人たちをご紹介していきます。
義民 増田 五郎右衛門(ますだごろうえもん)
首斬正月の弔いと戦後の五郎祭
増田五郎右衛門は、安永5年(1776)島田市細島村の名主の家に生まれました。この時代、特に文化年間(1804)に入ってからは凶作続きで、特に文化13年は、暴風雨のため困窮した農民は各地で年貢減免の一揆を起こしました。
田中藩の村々も、藩に年貢の減免を願い出ましたが、藩の財政もひっ迫しており拒否されてしまいました。
藩主に減免を直訴
このため五郎右衛門は、仲間と相談し、11月23日に藩主に直訴することを決め、藤枝の天神山に76ヵ村4、5000人の農民が集まりました。五郎右衛門は藩から派遣された責任者と話し合い、群衆を説得。一旦帰村し、藩からの措置を待つこととし、10分の3の減免が認められました。しかし、藩は一揆の首謀者の逮捕に乗り出し、無実の農民数十人を投獄しました。
五郎右衛門は全責任を一身に負って自首。2年後の文政元年(1818)6月28日に藤枝の源昌寺原の刑場で斬首となり、細島村の屋敷も焼き払われました。時に42歳でした。
五郎右衛門の処刑を悲しんだ農民はその遺骸をもらい受け、処刑人には禁じられている法号「義山玄忠居士」を贈って葬り、以後処刑された6月28日(現7月28日)を、首斬正月とし、農作業を休み、墓参してその菩提を弔いました。
各地に小堂や記念碑
源昌寺の裏には、五郎右衛門の冥福を祈るため、首斬り地蔵という小堂が立てられました。現在は毎年8月24日の地蔵盆に供養祭りが行われています。
明治17年、自由民権運動家らが新聞に、「義人増田五郎右衛門君建碑資金募集」の広告を出して資金を集め、翌18年、一揆ゆかりの地である天神山下(藤枝市藤枝5丁目)に「増田五郎君之碑」を建ててその事績を世に広(ひろ)めました。
大正13年、細島の全仲寺にある墓石の隣に「故増田五郎右衛門之碑」が建てられました。墓石は昭和59年に増田五郎右衛門顕彰会が新設しました。
また、大正15年には、細島の八幡神社境内に「義人碑」が、建てられました。
GHQ主導で五郎祭
戦後、日本の民主化を(を)促進していたGHQ静岡民事部は、この五郎右衛門の事績を知ると、民主主義を広める絶好の材料と考え、県と志太郡に働きかけて民主祭としての「五郎祭」を数年間開催しました。島田市東町では、現在も顕彰会によって墓前祭碑前祭(7月下旬)が行われています。