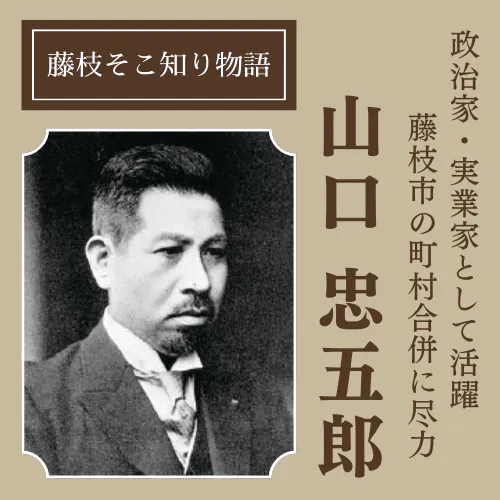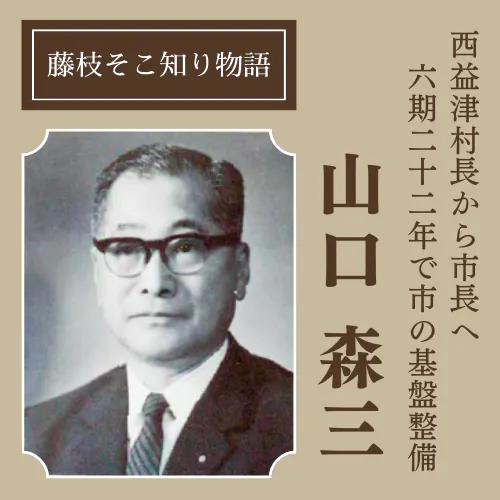藤枝市は、令和6年1月1日に、昭和29年の市制施行から70年、そして大正13年を起源とするサッカーのまちとしての歩みも100年となる記念すべき年を迎えました。
これまでに数多くの偉人たちが藤枝に関わってきました。
このコーナーでは、藤枝に纏わる様々な偉人たちをご紹介していきます。
静岡の大岡越前 松岡萬と岡部・松岡神社
県内2ヶ所に松岡の神社
藤枝市旧岡部町の廻沢に飛龍神社があります。古くから水神として、深い信仰を集めていました。そして、その隣には、幕臣松岡萬を祀った松岡神社があります。この神社は、明治3年、松岡が存命中に廻沢の人々がその徳を慕い、生き神として祀ったもので、こうしたものを生祠(せいし)といいます。県内にはもう1ヶ所、同様に松岡萬を祀った生祠池主神社(いけぬしじんじゃ)が磐田市にあります。
藤枝市民の憩いの場となっている蓮華寺池には、かつて干拓事業の騒動があり、これを治めたのも松岡でした。公園内には、その時の3人の名主の顕彰碑が建ち、碑記銘文中には松岡萬の名前が記されています。
松岡の静岡での四年間
松岡萬は天保9年(1838)、江戸の代々鷹匠組頭をつとめる家に生まれました。萬は「つもる」「むつみ」「よろず」とも読みます。
松岡は講武所に学び、勘定吟味役を経て、幕府精鋭隊に属しました。明治維新後、徳川慶喜の駿府移住の時、新番組頭として警護を務めた人物です。また水利路程掛・製塩方・開墾方等の責任者となって、中條金之助らと牧之原や富士山麓の開墾を指揮しました。
さらに、新門(しんもん)辰五郎の協力を得て、福田町の製塩事業なども行い、各地の農民たちからは、「松岡さま」と慕われました。
廻沢の松岡裁きと伝承
明治2年、岡部宿と廻沢村が入会地(いりあいち)の境界を定めるにあたって争いが起こりました。廻沢は大変小規模で、岡部宿からの境界の侵略は村の存立にかかわるものでした。明治3年、松岡の裁定で廻沢村の所有地が確定、廻沢村では飛龍神社内に松岡神社を創建。地元には松岡を称えたご詠歌が伝わっています。「まつおかさまの ごおんけい こころにちかい わするまじ ひりゅうじんじゃと もろともに」。
松岡は明治維新の功労者・山岡鉄舟の親友であり、侠客(きょうかく)・清水次郎長とも交流がありました。その後、警視庁の大警部を務め、明治24年没しました。享年54歳。