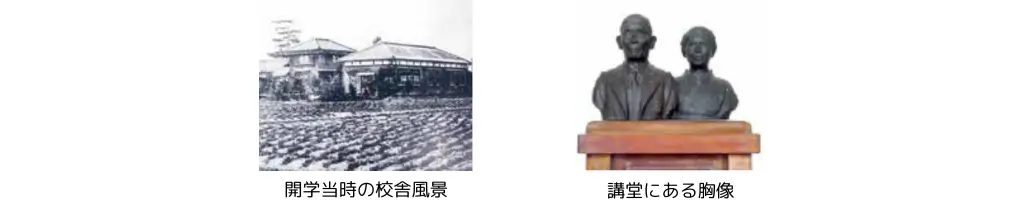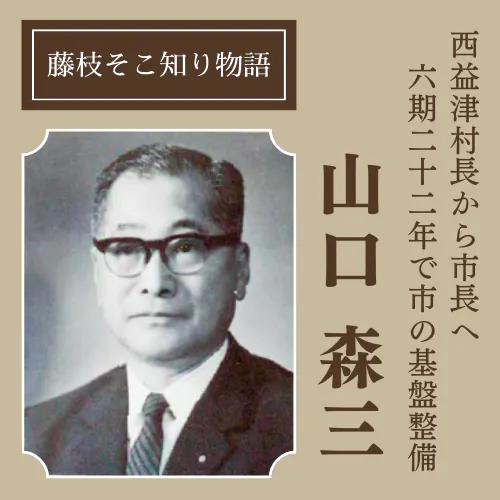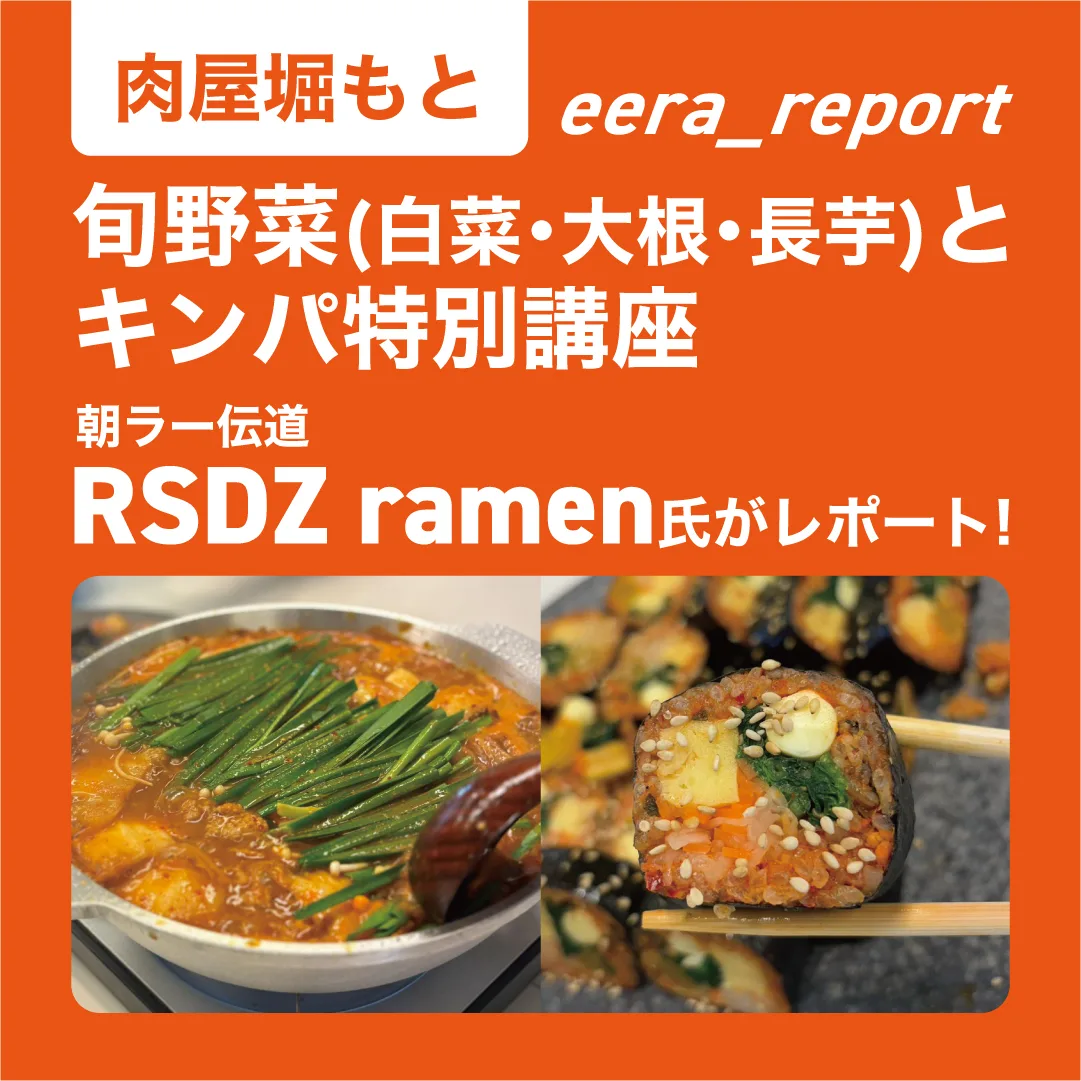藤枝市は、令和6年1月1日に、昭和29年の市制施行から70年、そして大正13年を起源とするサッカーのまちとしての歩みも100年となる記念すべき年を迎えました。
これまでに数多くの偉人たちが藤枝に関わってきました。
このコーナーでは、藤枝に纏わる様々な偉人たちをご紹介していきます。
教育者・仲田順光
藤枝順心高校の創立者・女子教育の発展に貢献
仲田順光は、明治26年(1893)10月愛知県西尾市米津町にある宝永寺に生れました。同30年4歳の時、実母と養父長谷川尭本に連れられ、静岡市丸子の向宮山小野寺に移り、長谷川たきとなりました。5才の時、青島村前島の退玄庵の仲田智光尼のもとに預けられ厳しく育てられ19歳のとき、養女となり、仲田順光となりました。
静岡高等裁縫女学校に
その頃の女子教育は「女に学問は必要ない。機織と裁縫が出来れば良し」という時代でした。尼寺は地域の女子を集めて機織や裁縫、躾を教える場所でもありました。順光は、教育がなく、技術を持たない女性の悲惨な生活を聞くにつけ、これからは、時代に即した技術を身に付けなければと思うようになりました。実兄の力蔵の勧めもあって養母を説得し、養蚕、茶摘みなどで7年間ため続けた資金で静岡高等裁縫女学校に学びました。その頃は、個人教授方式でしたので、順光は、自分の課題を進めながら、隣人を教える師の言葉を聞き取り、その夜隣人の教わっているものを紙裁ちして形を作り習得していきました。生活態度も養母に厳しく躾けられたため、朝起きて教室に出向き、窓にハタキをかけ、廊下と畳に雑巾をかけ、一度宿舎に帰って、寄宿の掃除をして、再び教室に通いました。この頃平塚雷鳥の「原始女性は太陽であった」という言葉に出会い、女性自立への意を強くしました。
仲田裁縫教授所開設
卒業した大正元年9月、仲田裁縫教授所を開設。時の青島村長山内与十郎と国会議員の青地雄太郎も出資し、開所に協力しました。また、最新の技術を習得するため、東京の大妻技芸伝習所(現在の大妻女子大学)の夏季講座に毎年出席しました。大正11年、鈴木恵法と結婚、媒酌人は、志太郡長の児玉九一でした。結婚の翌大正12年、校主仲田恵法、校長仲田順光として青島高等裁縫女学校を開校。入学希望者が殺到し、2年後には校舎を増築するほどでした。
藤枝南女子高から順心へ
昭和19年、青島女子商業高校とし、同23年、青島家庭高等学校に昇格し、女子中学校を併設。同27年付属幼稚園を設立し、幼児教育にも貢献しました。同29年に藤枝南女子高等学校となりました。同38年、文部大臣教育功労者として表彰、同46年には、勲四等瑞宝章を受章しました。そして同49年11月19日永眠。81歳でした。12月15日の学校葬では、菊で白梅がかたどられ、会葬者は2500名を数えました。法名は、興学院育英順光禅尼。平成15年、同校は、校名を藤枝順心高校としました。